
こんにちは。藤本です。
先日オンラインセミナーを実施しました。
といっても一般向けではなく、ライティング講座を修了した方向けのセミナーです。
このセミナーの様子は、今後ライティング講座を修了した方への特典としてお渡しする予定です。
そのセミナーでお伝えした内容のうち、一般向けにも理解してもらいたいことがあるので、今回はまとめてみたいと思います。
それは、ライティングで目標スコアを獲得するまでに必要な5ステップというものです。
1.基本を身につける
2.正解を知る
3.仕込む
4.質的な基準を作る
5.量的な基準を作る
この5つのステップですが、この順番通りに取り組むことが必要です。
1をおろそかにして、2や3ばかり取り組んでもスコアは上がらないし、4を行わずに5ばかり行ってもなかなか上がりません。
ということで、1つずつ見ていきます。
分かりやすくするため、ここではライティングの目標スコアを7.0に設定しています。
1.基本を身につける
ここで言う「基本」とは何かというと「文法」です。
ステップ1は正しい文法力を身につけましょう、ということです。
このステップが必要な人は、ライティングで4つある採点基準のうち、Grammatical range and Accuracy(以下GA)で7点が獲得できていない場合です。
GAで7点が獲れていない場合は、何かしらの文法的な間違いや、不自然な言い回しが含まれていると考えましょう。
正直、IELTS受験者の90%以上は、GAで7点は獲れていないと思います。
なので、ほぼ全員がここからスタートしなければなりません。
ここで必要なのは、文法ミスなしに英文が書ける、ということです。
文法ミスがある場合、たとえ内容的には素晴らしい内容であったとしても、採点官に伝わらない可能性があります。
採点官が内容を全く判別出来ない場合、当然ですが、Task Response(以下TR)、Coherence and Cohesion(以下CC)といった別の項目も「書けていない」という判断がされ、連動してスコアが下がってしまいます。
相手に伝わる英文を書く、というのは4つの採点基準すべてに共通する最低レベルの話です。
ここをまずはしっかりと取り組みましょう。
ライティングで文法ミスをしないとは、間違った英文を書いてしまったときに自分で修正できる、ということでもあります。
可算名詞単数形で冠詞がついていない
主語と述語の単複が一致していない
節と節の間に接続詞がない
名詞と名詞の間に前置詞がない
能動態であるべきなのに受動態になっている
関係代名詞の選択がおかしい
比較級の使い方がおかしい、などなど
読者に意味が伝わらないような英文は、見た瞬間に修正できるような、自己修正力をつける必要があります。
まずは、IELTS以前に、伝わる英文を書ける力を身につけておく、ということです。
具体的な方法は以下をご覧下さい。

2.正解を知る
次のステップが、IELTSにおいて何が正解かを知ることです。
つまり、何が評価されて、何が評価されないか、を知ることです。
このステップが必要な人は、ライティングで4つある採点基準のうち、TA/TRと、CCで7点が獲得できていない場合です。
TA/TRやCCで7点が獲れていない場合は、設問で求められていることや、採点基準で必要と書かれていることが書けておらず、減点されている、ということです。
ですから、その場合はまずIELTSは何が求められて、どう書くのが正解なのかを知る必要があります。
このポイントで特に気をつけたいのが、特にスコアが低いうち(ライティングスコア6.0以下)は、プラスを目指すよりもマイナスを減らすということです。
マイナスを埋められていないうちに、プラスを目指しても、それは評価されません。
マイナスが気にならないような文章になった後にやっとプラスを評価する、という段階に入ります。
だから、巷でよく言われる、難しい単語を使うとか、複雑な構文を使う、というのは一旦後回しです。
そこに時間を使うなら、まずマイナス評価されている箇所を無くす方が圧倒的に先決です。
闇雲にIELTSの対策をする前に、まずはどこを目指したら良いのかというゴールを明確にする、ということですね。
採点基準を完全に理解するようにします。
表面的な理解ではなく、具体的にどんな書き方になると減点になるかをしっかりと頭に入れます。
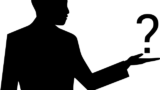

3.仕込む
次のステップが、IELTSに必要な「展開パターン」と「表現」を覚える、ということです。
このステップで目指すのは、「IELTSの設問を見た瞬間に展開パターンが思い浮かぶ」ということと、「覚えた表現だけを使って、すべてを表現できる」という状態を作ることです。
ここで言う「展開パターン」とは、例えば以下のようなイメージです。
アカデミックのTask1で、時系列の折れ線グラフが出題されたときは、
「左上に位置しているデータから説明を始める」
↓
「時系列のスタート時点のデータを説明するときに一緒に順位の説明を行う」
↓
「その後、時系列に沿って増減の変化を説明する」
↓
「増減の変化を説明した後に、順位の変動があればそれを同時に説明する」

Task2で「目的に対する手段の良し悪し」を問われている問題を見たときに、賛成のサポート意見であれば
「この手段は目的に対して効果的である」
「この手段は主目的以外にも副次的効果をもたらす」
「この手段を求めている人がいる」
「この手段は簡単に実施できる」
といった切り口でアイデアを述べる
このような展開パターンを完全に頭に入れておけば、設計時間を短縮することも出来、かつ減点の少ない展開パターンで書くことが出来ます。

次に「表現」の方ですが、こちらは必要なシーンに応じて、いくつかの構文と単語を取り出せるようにしておく、ということです。
例えばアカデミックTask1で円グラフが出て、シェアの表現が必要になったときに
The share/ratio/proportion of A is ~%
A account for/make up/represent ~%
~% of people belong to A
といった表現が瞬時に複数書けるように覚えておく、ということです。
Task2であれば、因果関係の表現を連発するわけですが、このときに
主節+従属節(if/when/since/because/as)
主節+副詞句(due to/by+動名詞/with/because of)
無生物主語(lead to/bring about/cause/result in)
といった表現が瞬時に複数書けるように覚えておく、ということです。

こういった表現はライティングノートにまとめて、一問一答形式で確認できるようにまとめていきます。
そして暇があれば、そのノートを見て記憶を確固たるものにしていきます。


ライティングはその場でオリジナルで考えたような文章を書くと、ほとんどのケースで、間違いを含んでしまうか、不自然な表現になります。
だからまずは間違いのない表現を覚えてしまうのです。
そしてその「間違いのない、安全な表現」だけを使って、英文を表現するようにします。
Task1もTask2も、それほど複雑な表現を使う必要はありません。
一定量の表現を覚えてしまえば、その「安全な表現」だけを使って、すべてを表現できるようになります。
ステップ3の仕込み作業では「適切な展開パターン」と「安全な表現」を徹底して暗記していきます。
4.質的な基準を作る
4つ目のステップは、質的な基準を作る、というものです。
このステップで目標にするのが
「時間さえかけて書けば7.0が出せる」
という状態を作ることです。
多くの方が、本番で目標スコアが出ないのは時間が無いせいだ、と考えています。
しかし、実際は違います。
添削などで目一杯時間をかけて書いたとしても目標スコアは出ずに6.0や6.5でとどまるケースは多いのです。
そこには
・自分では気付いていない文法ミスがある
・知らず知らずのうちにIELTSの減点ポイントに抵触している
・文章をオリジナルで作って、不自然な表現になっている
といった課題があります。

だからどんなに時間をかけて、どんなに100点だと思う内容を書けたとしても、実は目標点には及ばない品質だったりします。
例えるなら、自分が100点だと思っている基準が、客観的には60点だった、という状態です。
この状態で、どれだけ受験しようが、どれだけ時間内に早く書く練習をしようが、目標スコアが出ることはありません。
だからまず自分の基準を引き上げなければなりません。
そのためには、まず時間をかけて書いてみて、そしてその文章を添削してもらうことです。
そこで、何が自分に足らないのかを冷静に見極めて、自分が目標にしているスコアのライティングとはどのような品質のものかを理解する必要があります。
ここで、文法が弱ければステップ1に、採点基準の理解が甘ければステップ2に、自分が覚えている表現だけですべてが書けなければステップ3に戻ります。
そして、各ステップを万全にしたうえでステップ4で、目標スコアが添削上で出るまで繰り返します。
5.量的な基準を作る
最後のステップは、時間をかけて書いた場合は添削で7.0が出るのに、本番では7.0が出ない場合です。
ステップ4までで自分の基準はすでに目標レベルに到達しているはずですから、最後のステップはその品質を時間内で出すことだけに集中します。
この段階では、制限時間内に設計し、記述していく練習を繰り返すのみです。
ここで気をつけなければならないのが、制限時間を意識するあまり、ステップ4まで積み上げてきた書き方が崩れてしまうケースです。
時間を意識して、オリジナルの文章を書いてみたり、展開パターンを無視した書き方になってしまったりすると、かえって目標は遠のきます。
あくまでステップ4まで積み上げてきた方法に固執して、時間だけを短時間化していきます。
まとめ
いかがでしょうか?
1.基本を身につける
2.正解を知る
3.仕込む
4.質的な基準を作る
5.量的な基準を作る
という5ステップを順に積み上げてスコアを上げていくという考え方はとても重要だと思います。
もし、この順番を間違えたり、先に行うべきことを忘れている場合は、是非この順番を意識して対策を立ててみて下さい。

