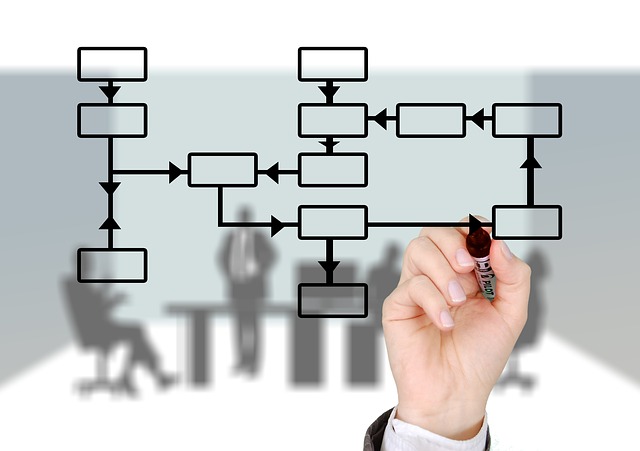こんにちは。藤本です。
ここ最近、アカデミックTask1についての説明を書いています。
ここまでの記事はこちらから。


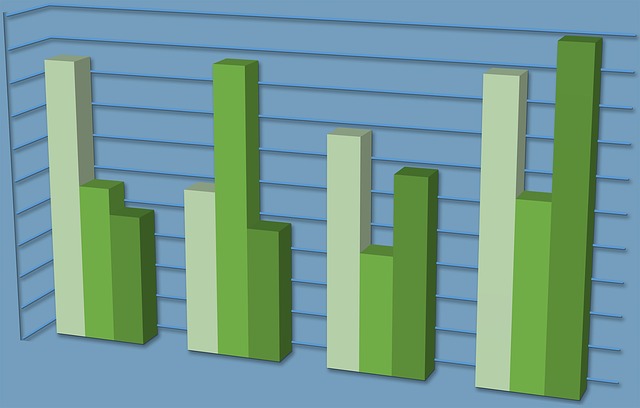
さて、本日はアカデミックTask1でときどき出題される地図問題について見てみましょう。
地図問題の概要
地図問題の多くは、2枚の地図が出ます。
古い時期の地図と新しい時期の地図が表示されて、それらを比較する問題が一般的な地図問題です。
以降は、この典型的な地図問題を題材に説明してみます。
オーバービューの書き方
2枚地図の問題でオーバービューに書く内容は、以下のように考えると汎用性があります。
1.おおまかにいくつぐらいの変化があったか
2.変化の方向性はどのような方向性か
例えば
「3つの大きな変化によって町が都会化した」
といった感じですね。
変化の方向性としては、「都会化」「工業化」「商業化」「拡大」などが考えられます。
ボディの書き方
2枚地図の場合、最初のボディに古い時期の地図についての説明を書き、2つ目のボディに、新しい時期の地図が、どのような変化を起こしたかを書くと、書きやすいです。
ボディ1の古い時期の地図に関しては、地図上に書かれているすべての建物、設備、エリアなどを説明していきます。
ここでのポイントは、それぞれの要素の位置関係です。
何がどこにあるかを地図が見ていない人にも伝わるように書いていきます。
一方、ボディ2の新しい地図は、古い地図と比較したときの変化情報を書いていきます。
変化の方向性は基本的に5つ
・加えられた
・無くなった
・大きくなった
・小さくなった
・入れ替わった
です。
こういった変化を説明していきます。
地図問題の落とし穴とコツ
地図問題でよくやってしまう間違いをいくつか書いてみましょう。
位置関係の説明が伝わらない
例えば
「この地図の南東に工場があります。そして、この地図の南側には川が流れています。」
という説明があったときに、工場と川のどちらがより南にあるのか、位置関係がよく分かりません。
この原因は、工場も、川も、地図の中でどの方角にあるかが説明されているだけ、ということです。
これを解消するには、既に説明したものから見た相対的な位置関係を使って説明してあげることです。
「この地図の南東に工場があります。そして、その工場の南側には川が流れています。」
こう説明するだけで、より明確な位置関係が伝わります。
まだ説明していないものを前提にした説明をしない
「道路Cは、建物Aから建物Bまで延びています。建物Aは、地図の中心にあり、建物Bは、建物Aから東側に位置しています。」
こんな説明があったとき、果たして頭から読んで、地図が再現できるでしょうか?
道路Cの説明をしている段階では、読者は建物Aの位置もBの位置も分かりません。
その状態で、道路Cの説明をしても、頭に入ってこないのです。
「建物Aは、地図の中心にあり、建物Bは、建物Aから東側に位置しています。道路Cは、その建物Aから建物Bまで延びています。」
こういった説明の方が圧倒的に読者にとって分かりやすいですよね。
変化の数が一致しない
オーバービューで大まかな変化の数について書くという話をしました。
ところが、その変化が何を指しているのかが、ボディ2を読んでも分からない、というケースがあります。
3つの変化があると書いてあるのに、ボディ2を読むと、どう読んでも4つ変化があるようにしか見えない場合があります。
ボディ2で書く変化の数は、オーバービューで挙げた変化の数に合わせた形で書きましょう。
ということで、本日は「地図問題」について見てみました。
次回は「フローチャート問題」についてまとめてみたいと思います。