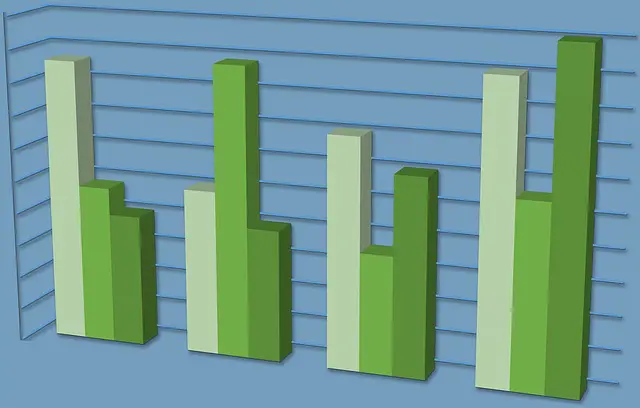
こんにちは。藤本です。
前回アカデミックモジュールのライティングTask1について、時系列グラフの書き方についてまとめてみました。

今回は、時系列の概念が入っていないパターンのグラフ・表についてまとめてみます。
時系列でない図表とは、例えば
「ある国における8つの職業の男女別人数を示した棒グラフ」
「縦軸が5つの国の名前、横軸に人口・GDP・犯罪率の項目があり、中身にそれぞれの数値が入っている表」
のようなものが典型的なイメージです。
以下これらのグラフを題材に説明していきます。
目次
オーバービューの書き方
時系列でない図表についてオーバービューで書くことは、それぞれの項目で一番大きなものについて書く、というのが、一番汎用性がある書き方です。
例えば
「ある国における8つの職業の男女別人数の棒グラフ」
であれば
「男性で一番多いのは〇〇という職業である一方で、女性は〇〇が一番多い」
という感じですね。
「縦軸が5つの国の名前、横軸に人口・GDP・犯罪率の項目がある表」
であれば各項目ごとのトップを挙げるイメージで、
「人口で一番多い国は〇〇、GDPで一番多いのは〇〇、犯罪率が一番高いのは〇〇」
といった感じです。
非時系列の表形式のボディの書き方
「縦軸が5つの国の名前、横軸に人口・GDP・犯罪率の項目がある表」においてやってはいけないのが、国でボディを分けるという書き方です。
例えば、5つの国のうちの3つをボディ1で触れて、残りの2つをボディ2で触れるというやり方をすると、どのデータを説明すべきかが分かりにくく、結局全部のデータを説明するという感じになってしまいます。
こうなると流れも悪いし、メリハリも効きません。
「プレーヤー×項目」という表においては、「プレーヤー」ごとではなく、「項目」ごとに説明していくようにします。
なので、この場合、例えば「人口」と「GDP」をボディ1で説明して、「犯罪率」をボディ2で説明するようにします。
各項目ごとの説明ですが、一番大きな(目立つ)数字を持つ国を説明して、残りはグルーピングを上手く使って説明します。
例えば
「人口でダントツに多いのはAで5000万人。残りの4か国は3000万人以下である」
「GDPで一番多いのはBで〇〇億ドル、2番目はCでBの半分の〇〇億ドルで、残りの3か国はさらに少なくて〇〇億ドル前後で類似している」
とか、そんなイメージです。
「~以上」「~以下」「~前後」といったグルーピングをするのがコツです。
非時系列の棒グラフのボディの書き方
「ある国における8つの職業の男女別人数の棒グラフ」のようなグラフで、「男女」でボディを分けるのか、職業をグルーピングしてボディを分けるのかは、内容によりますが、何かしらの基準でグルーピングして説明していくことになります。
ここでは、男性の特徴をボディ1、女性の特徴をボディ2で書いていくことにしましょう。
その場合、ボディ1では、男性の一番人数が多い職業から説明を始めて、3-4グループに分類しながら説明していきます。
例えば
「男性で一番人数が多い職業は〇〇で10万人。それに続く第2グループが〇〇と〇〇で、それぞれ7万人と6万人。第3グループは4万人前後で〇〇と〇〇と〇〇。一方で、残る4つの職業(〇〇、〇〇、〇〇、〇〇)は少なくて、2万人以下である」
こんなイメージですね。
ボディ2の女性の説明は、基本的に男性と同じですが、全く同じ説明を続けると単調になるので、ボディ1の男性の数字との比較を入れていくようにします。
「女性で一番多いのは〇〇で、同じ職業の男性の人数の約5倍で8万人」
みたいな感じですね。
非時系列グラフの落とし穴
1.補足情報のみを説明してしまう
時系列でない図表の場合、「増減」の説明が出来ません。
そうでなければ「順位・大きさ」とか「類似性」とか他の特徴を説明しなければなりませんが、ついついそれらを怠って、補足情報(データ)の説明のみに終始してしまうケースがあります。
例えば
「Aの人口は〇〇人、Bの人口は〇〇人、Cの人口は〇〇人・・・」
のように、ひたすらデータの説明だけが続き、大きいのか小さいのか、似ているのか似ていないのかの特徴の説明が一切ない文章になってしまいがちです。
2.小さくてどうでもよい情報を詳しく説明する
時系列でない図表は、基本的には数値の大きな、目立つ特徴から説明していきます。
逆に、数値の小さな、目立たない特徴は、優先度が下がります。
目立つ特徴はしっかり伝えたいですが、数値の小さな箇所については、グルーピングするなどして、さらっと流した方が良いです。
3.相関関係など高度な分析をしようとする
時系列のように「増減」という分かりやすい特徴が使えないときに、各項目間で相関関係があることを説明しようとして、自滅してしまうケースがあります。
データに綺麗な相関関係があるケースはあまりなく、それよりは、単純な「順位・大きさ」や「類似性」を記載していった方がシンプルで書きやすいです。
ということで、前回と今回で、グラフ・表形式の書き方についてまとめてみました。
次はアカデミックのTask1の2番目のパターンである「地図」についてまとめてみたいと思います。




