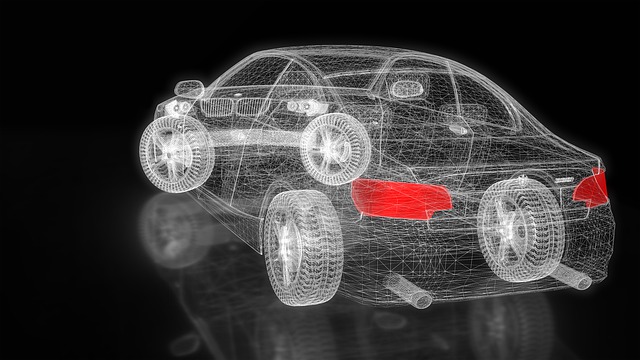
こんにちは。藤本です。
アカデミックライティングTask1シリーズ、今回が最終回です。
これまでの記事はこちら。


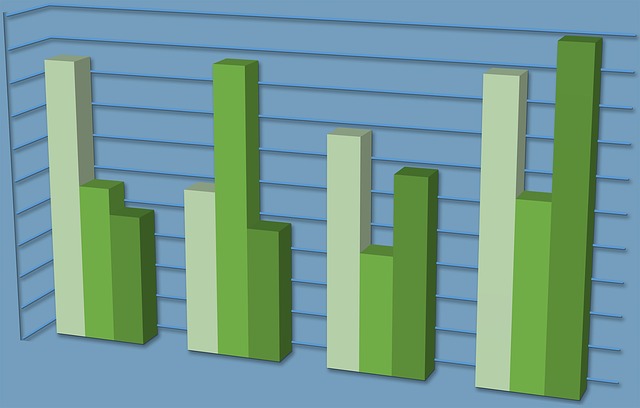

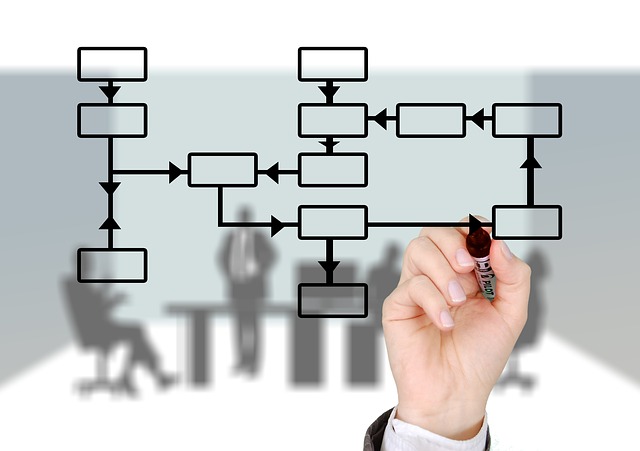
さて、本日は装置構造図について書いてみます。
このタイプは滅多に出題されません。
数年に一度程度しか出ませんが、出たら結構苦労するのが、このタイプです。
ですが、パターンを確立してしまえば割と簡単に記載が可能です。
装置構造図の概要
装置構造図問題は、何かの道具やデバイスの分解図が出ます。
そのデバイスを構成している部品や、動作の仕方が図で説明されています。
オーバービューの書き方
装置構造図のオーバービューは、以下の2つの要素で書くと汎用性があります。
1.大まかなパーツ数
2.ざっくりとした動作
例えば
「このデバイスは、大きく3つのパーツで出来ており、〇〇な動作をする」
といった感じのオーバービューです。
ボディの書き方
装置構造図は、ボディ1で「構造」について、ボディ2で「動作」について書くとまとめやすいです。
ボディ1の「構造」では、図に出てくるパーツの位置関係を説明していきます。
基本的に図に出てくるパーツはすべて使って説明をしていきます。
ボディ2の「動作」では、それぞれのパーツがどう働いて動作するのかを説明します。
装置構造図の落とし穴とコツ
装置構造図で気をつけなければならないポイントを書いておきましょう。
大まかなところから細かいところに
特にボディ1で構造を説明する際の注意点ですが、いきなり細かいところから説明すると、読み手が分かりにくくなります。
例えば
「まずAというパーツがあり、そのパーツの中にはB,C,Dというパーツがあり、そのBとCはEによってつなげられている。次にFというパーツがAの隣にあり、・・・」
という説明と
「このデバイスは大きくAというパーツとその隣に位置するFというパーツで出来ている。Aというパーツの中にはB,C,Dというパーツがあり、そのBとCはEによってつなげられている。」
という説明では、後者の方が分かりやすいと思います。
最初に大まかな全体像を示してあげて、その上でディテールにフォーカスするように説明していくと良いです。
まだ説明していないものを前提にした説明をしない
もう1つ構造を説明するときの注意点です。
「Aというパーツからロープが伸びていて、その先にBというパーツがある。BはAの上に位置している。」
という説明を読んだときに、少し混乱しないでしょうか?
その理由は、ロープが伸びた先にあるBというパーツをまだ説明していないのに、その説明していないBに向かってロープが伸びているという説明になっているため、Bがどこにあるか分からないままロープが伸びているイメージをしなければならないからです。
基本的に、まだ説明していないものを前提にした説明は避けます。
最初の例で言えば
「Aというパーツがあり、BはAの上に位置している。そして、そのAとBをロープがつないでいる。」
という順序で説明すると、こういった混乱がなくなります。
原動力から話を始める
ボディ2の注意点は、必ず原動力から話を始めるということです。
どの装置構造図も、そのデバイスが動くための一番の原動力や最初のきっかけがあります。
車ならアクセルを踏むことが車が動くきっかけになりますね。
自転車ならペダルを踏むことが原動力です。
その原動力から話をスタートさせて、その力が伝わる順番に説明をしていきます。
そうすることで、動作をスムーズに説明することができます。
ということで、アカデミックライティングTask1の書き方について、連載してみました。
ご参考になれば幸いです。
