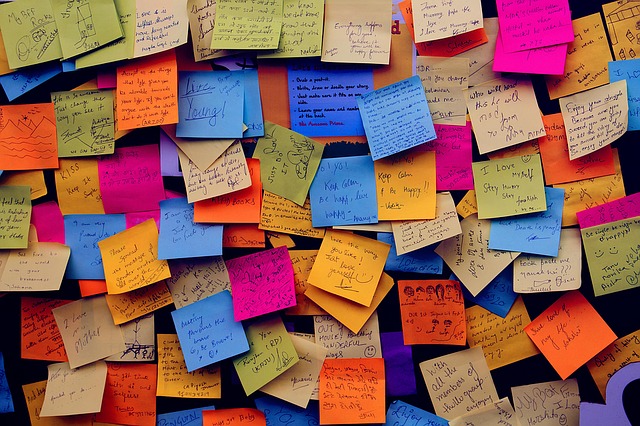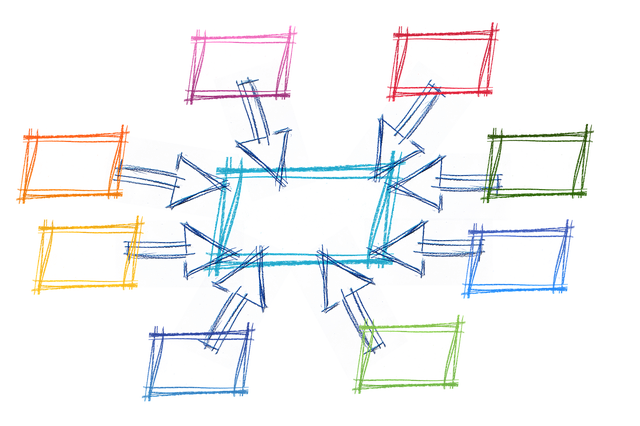
こんにちは。藤本です。
リーディング対策にはある程度段階があります。
最初にぶつかる問題が単語。
単語がよく分からないので、読み進められないし、意味も分からない。
この段階は単語を覚えるしかないですね。
基本的な単語を覚えて知らない単語が出てくる確率が一定以下に下がれば、文章が理解できる割合が高まります。
次にぶつかる問題が構文。
簡単な構文なら分かるけど、ちょっと複雑になるとよく分からない。
これは、自分の中にパターンがある構文とパターンがない構文があって、パターンがない構文にぶつかると2回以上読まないと理解できない、というケースです。
これは様々な構文を覚えて、自分の中にパターンを作っていくと解消できるようになります。
さて、今日は次の問題です。
単語の問題は覚えてある程度解消された、構文もある程度一発で取れる、そうなるととりあえず1つ1つの文章は理解できるようになります。
しかし、パラグラフやパッセージを読み終わったときに、何を書いていたのか、著者は何を言いたかったのかがよく分からない、そんなケースです。
この問題のポイントは、パラグラフ構造を捉えることです。
英文のパラグラフには、基本的にはその一文を読めば、パラグラフ全体で何を言いたいかが分かるトピックセンテンスという一文が入っています。
そして、残りのセンテンスは、そのトピックセンテンスをより具体的に展開したものや、トピックセンテンスで述べた主張の理由を述べるセンテンスになっています。
言わば、トピックセンテンスが親、その他のセンテンスが子供、の関係です。
その親子関係を意識しながら読んでいくと、パラグラフ構造がとても立体的に見えてきます。
こうなればしめたもので、著者が言いたいことが非常に頭に入ってきやすくなります。
ではそのトピックセンテンスはどう捉えたら良いでしょうか?
私のリーディング対策講座では、そのパターンを5つに分類してしています。
なので、そのどれかにあてはまると考えていけばトピックセンテンスは捉えられます。
ただ、その5つの中で圧倒的に高い確率で出るパターンがあります。
それが文頭の一文がトピックセンテンスというパターンです。
文頭にトピックセンテンス、その後に、具体例や、主張の理由が示される、という流れですね。
この文頭タイプが、トピックセンテンスとしては圧倒的に多いので、パラグラフを読むときは、まずは文頭がトピックセンテンスではないかと疑って読み始めます。
その一文で、「今からこんな話をしますよー」という”予告”っぽい内容になっていたり、その前のパラグラフとは異なる話をして”話題転換”をしていたり、著者の”主張”が入っていたりする場合は、その時点でトピックセンテンスです。
後はそのトピックセンテンスを展開する内容が続くはずです。
こんな読み方を常にしていると、極端に言えば、パラグラフの中で次にどんな展開がされるのかが予想できるようになります。
その予想を確認しながら読む、というスタイルで読んでいけば、パラグラフ全体で何を言いたいかが分からない、という問題は解消されるわけです。
こんな意識でリーディングの取り組みをしてみて下さいね。
そうすると、IELTSだけでなくて、留学した後に読む長文も楽に読めるようになりますよ。
Have a good day!