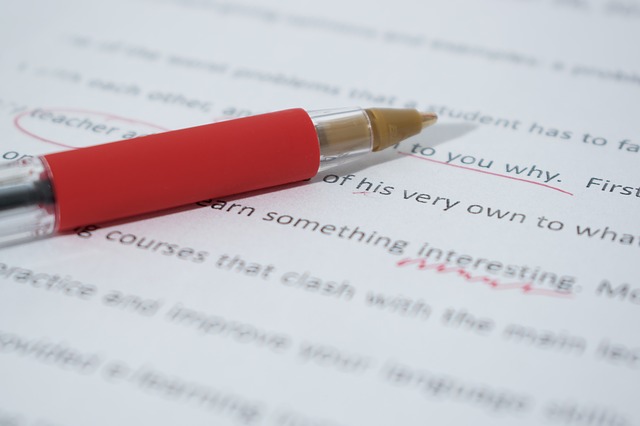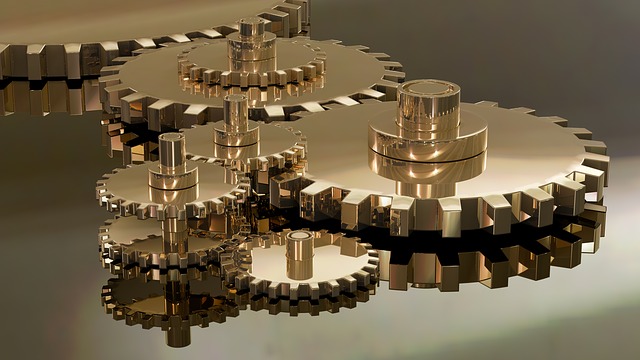
こんにちは。藤本です。
IELTSのライティングには、「論理の一貫性とまとまり」という採点基準があります。
ここで、論理的な展開が出来ているかが問われるわけですね。
ただ「論理的」と言われても、どんな文章が論理的で、どんな文章がそうでないのかは、ちょっと分かりにくい人もいるかもしれません。
よく言われるのが、つなぎ表現を使うという話です。
これは、分かりやすいですね。
それまでの内容を否定するなら、Howeverなどの逆接のつなぎ表現を使い、具体例を展開するなら、For exampleを使い、理由を説明するならbecauseを使います。
並列で2つのことを説明するなら、Firstly, Secondlyを使い、展開してきた結果を説明するなら、Thereforeを使えば良いわけです。
流れに沿ったつなぎ表現が自然な形で使えていればOKです。
もう1つ、指示語、代名詞の問題もありますね。
代名詞が何を指しているかが分からないと、話の流れがつかめず、論理展開が分からなくなります。
指示語については、こちらも参考にして下さい。

さて、よく言われるのはこの2つですが、この2つが完璧なら論理的というわけでもありません。
ここでは、主にTask2で、つなぎ表現、指示語以外で論理的でないと指摘される代表的なパターンについてまとめてみます。
1.トピックセンテンスが無い・トピックセンテンスに沿っていない
トピックセンテンスは、パラグラフの冒頭にパラグラフ全体を代表するような内容で記載します。
例えば以下のような文章があったとしましょう。
英語をマスターするにはいくつかのメリットがある。
最初のメリットは、英語で書かれた本を読めることである。
次のメリットは、英語圏での就職可能性が増えることである。
この文章の最初の1文がトピックセンテンスになっているのは分かるでしょうか?
「いくつかメリットがある」というのは、その下にある「最初のメリット」と「次のメリット」の概念を含んだ全体のまとめになっています。
こういったまとめ的な文章がトピックセンテンスです。
英文には、このトピックセンテンスが必要です。
このトピックセンテンスが無かったり、中身がトピックセンテンスに沿っていないと論理的とは言えなくなります。
2つの例を挙げてみましょう。
例1:トピックセンテンスが無い
英語をマスターする1つ目のメリットは、英語で書かれた本を読めることである。
もう1つのメリットは、英語圏での就職可能性が増えることである。
この文章は、トピックセンテンスがなく、いきなり1つめのメリットの話から入っています。
ではこの文章がトピックセンテンスになるかと言えば、次の文章で、2つ目のメリットの話になっています。
つまり、1つ目の文章はパラグラフ全体を包括する内容になっておらず、トピックセンテンスがないパラグラフになってしまっています。
例2:トピックセンテンスに沿っていない
英語をマスターするにはいくつかのメリットがある。
その1つは、英語で書かれた本を読めることである。
一方で、英語をマスターするには労力がかかる。
これを克服することが大切である。
このパラグラフは、最初のトピックセンテンスで「メリット」について述べると宣言しておきながら、途中で「労力がかかる」というメリットとは関係ない話に展開しています。
つまりこの内容だと、最初の1文がパラグラフ全体を代表しないことになってしまいます。
やはり論理的とは言えなくなります。
2.論理の飛躍がある
論理的でないと感じる文章の原因に、論理の飛躍があります。
これは、本当は「AだったらB、BだったらC、よってAだったらC」という順序で説明しなければならないのに、いきなり「AだからC」という書き方をしてしまうパターンです。
例を挙げます。
英語で書かれた本を読めると、知識が広がる
この展開に飛躍があることは分かりますか?
本当は
英語で書かれた本を読める。
英語で書かれた本の中には、母国語で書かれた本にはない情報がある。
そういった本を読むことで、母国語の本だけを読んでいた時に比べて広い知識が得られる。
というロジックになっています。
最初の文章は、「英語で書かれた本の中には、母国語で書かれた本にはない情報がある」という大切な前提条件が抜けてしまっているんですね。
そんなことは当たり前、書かなくても分かる、と思うかもしれません。
でも英語圏の人から見たら、果たしてそれは「当たり前」のことでしょうか?
中にはそう読み取ってくれる人もいるかもしれませんが、そうでない人もたくさんいます。
英語で発信されている情報は、どんな国の人でも知っている、という感覚を持っている人だっているわけです。
だから、そういった前提条件は、しっかり書いてあげないと、ロジックはつながらないわけです。
この論理の飛躍が激しい場合は、留学をして論文を書いたときに、相手に理解してもらえず、ひたすらWhy?と聞かれることになります。(私自身も経験済みです。。)
3.メリットとデメリットの比較がない
例えば、「メリットとデメリットのどちらが大きいか」という設問のときに、メリットが大きいという立場でエッセイを書くとしましょう。
この場合、最初のイントロダクションで、自分の立場を明らかにし、以降、メリットとデメリットについて展開していきます。
そして最後の結論で、再度自分の立場を述べますね。
図式化するとこんな感じです。
イントロダクション:メリットが大きい
ボディ1:デメリットについての説明
ボディ2:メリットについての説明
結論:メリットが大きい
このときの最後の結論の書き方が、論理的でない場合が多々見られます。
ボディ1でデメリットがあることを説明しました。
ボディ2でメリットがあることを説明しました。
この2つを受けて、結論で述べるのは、「メリットもデメリットもあることが分かったうえで、なぜメリットの方が、デメリットより大きいか」です。
ここで、あっさりと
「~というメリットがあるから、メリットの方が大きい」
と書いてしまう方が非常に多いです。
これは
「デメリットもあるし、メリットもあるが、メリットがあるからメリットの方が大きい」
と言っているようなもので、全く論理的ではありません。
ここも例を挙げましょう。
イントロ:英語をマスターすることはメリットが大きい
ボディ1:英語をマスターするにはデメリットもある(1.時間と労力がかかる、2.労力の割に使う場面が少ない)
ボディ2:英語をマスターするにはメリットがある(1.英語でしか学べない知識を得られる、2.就職可能性が増える)
結論:異文化のことが学べるし、就職可能性が増えるから、英語をマスターするのはメリットの方が大きい
こんな感じですね。
最後の結論が、論理的でないのは分かりますか?
ボディ1でデメリットがあるって言ったじゃん。そのデメリットはどこに行ったの?という感じです。
デメリットの大きさよりも、メリットの大きさが勝ることを言えて、初めて最後の結論が言えます。
例えば
結論:一時的には労力もかかるし、すぐに使える場面も少ないかもしれないが、長期的に見れば増えた知識は一生使えるし、国際化が進む中、海外就職の選択肢が増えるのは大きなメリットである。よって英語をマスターするのはメリットの方が大きい。
こんな感じで結論が書けると、デメリットとメリットを比較した上での結論なので、論理的と言えますね。
ということで、論理的な文章というのを具体例を挙げて見てみました。
文章が論理的かそうでないかというのは、指摘されないとなかなか気づきにくいです。
だからこそ、ライティングは、添削が重要なんですね。
添削は、単語の選択や、文法といった表現力だけでなく、こういった論理性も必ず添削をしてもらって下さいね。
Have a good day!